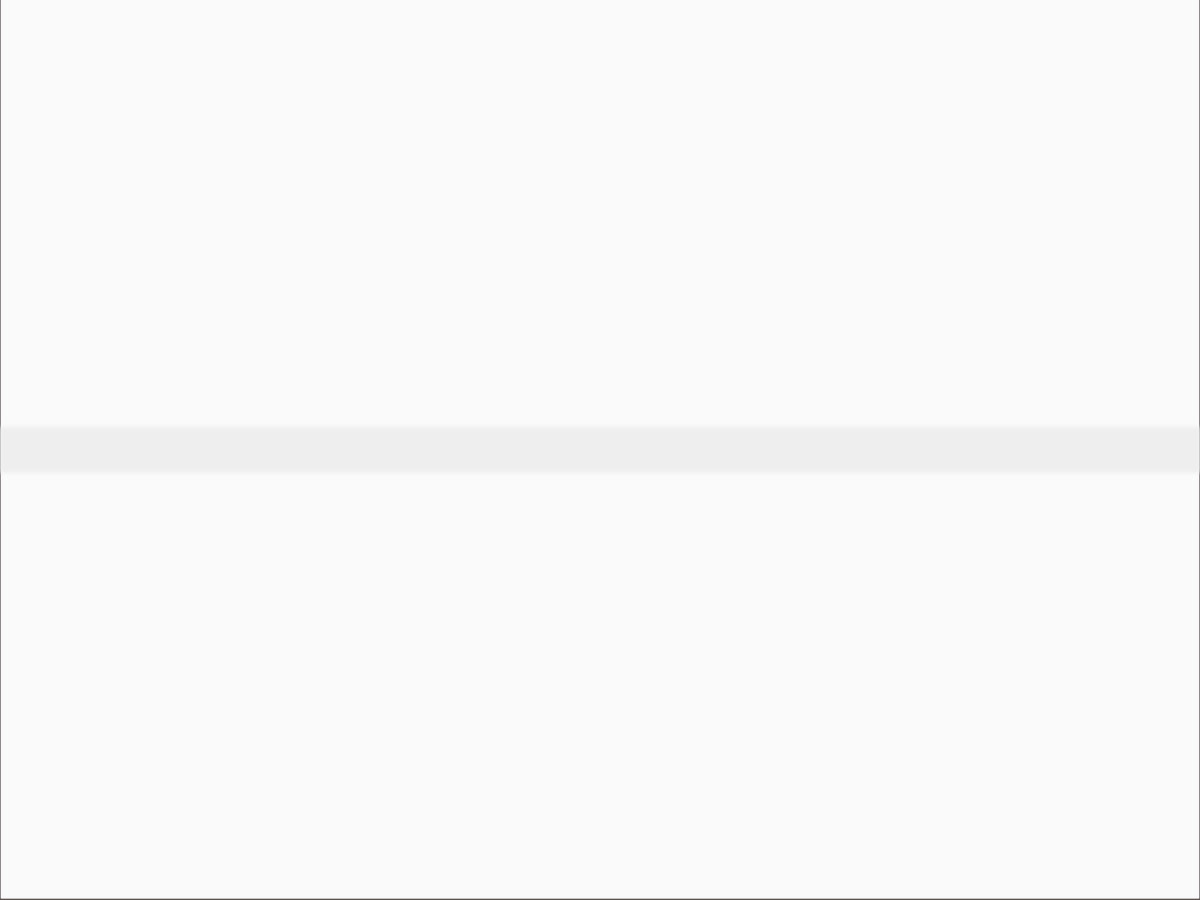前述のように、私が書くことばのなかの〈わたし〉という語は、それを読む他人にとってと、それを書く私自身にとってとでは、べつのしかたで機能しているようです。
読むひとにとっては、ひとつのヒトガタの目印として。
書く私にとっては、異物であり、かつ、私という場のなかに時おり隆起し、露出する、裂け目として。
〈わたし〉という語を蝶番のようにして、それをふくむ言説の空間が、読み手である他人と、書き手である私とに、向きあうようでありながら「ずれた」、非対称なかたちで現れているようです。
私の側からは、向こう側にいるはずの見えない相手――かみさまの空間に宛てて、投げかけるように、ことばを書いています。
向こう側では、書かれたことばを読みながら、時おり現れる〈わたし〉の語をとおして、紙ににじむ空間を見透かすかのように、〈わたし〉とイコールであるとされるヒトガタを見ているらしい。
でも私からは、その読みのまなざしは見えない。見えないながらも、ここにいる私と、いま読まれている文章のなかの〈わたし〉とは、決定的にずれているということはわかるのです。
書く/読むことばの空間をこんな構図でとらえるということが、そもそも的外れなのかもしれません。
もっと別の角度から、別の立ち位置や別の次元から、ちがう質のものとして、書くことばと、その機能のしかたをとらえることができたらいい、とも思います。
でも、実際、私がほかの誰かの書いたことばを読むときのことを考えてみると、やはり、そのなかの〈わたし〉という語をとおして、特定のひと(ヒトガタ)を思い、そのことば=読んでいる文字の「外」にいるはずのそのひとが生みだしたものとして、そのことばの全体を受けとっています。
そして、その書きぶりや内容に「そのひとらしさ」を勝手に感じとったり、「そのひと」について新たな発見をした(と思った)りしています。
そして、他人の書いた〈わたし〉構造のことばを私が読んでいる、まさにそのような読みかたで、私の書いた〈わたし〉構造のことばを他人が読んでいる、と思い浮かべると、なにか非常なつらさ、いたたまれなさを感じます。
これはもちろん、その読み手が抱く〈わたし〉の像=フジモトナホコという特定の人物の像が当たっているとか、ズレているとか、そういう話ではありません。
〈わたし〉という語が構造的に、本質的にはらんでしまうズレなのだと思います。
そしてこれは、私が、なぜかしらどうしても「わたしは……」というかたちでことばを書きたくなってしまうからこそ、起こるズレです。
でも、もしかしたら逆に、ここにこそ、〈わたし〉という語の、裂け目/露出部としての面白さがあるのかもしれない、とも感じます。他人が、私には見えない〈わたし〉を見ている。ずれている。なにかが露出しているらしい。――ここのことを考えようとすると、なにかが立ちはだかり、まだ、うまくとらえて考えられないのですが。
08 蝶番