私の書く〈わたし〉という語は、それを読む他人にとっては、「特定の名をもち、一個のカラダとして実在するはずの、あるひとりの人物」=「書き手」を想定させる語として機能するのだと思います。
私を知る人であればきっと、フジモトナホコという固有名や、そのひとの有するフジモトナホコに関する記憶や情報――そしてとくに、もし実際に会ったことや写真を見たことがあれば、そのカラダが実在するという確かさの感触――と自動的に結びついて、読まれるでしょう。
でも、私自身にとって、自分が書きつける〈わたし〉の語は、フジモトナホコという「人物」(ヒトガタ・輪郭)を指しはしません。
その語は、……なんだろう、なにを指しているのでしょうか。
どうやら、なにかを「指す」というのではない形で機能しているようにも思えます。
ことば(文章)を書くとき、その行為は、そのときの私の意識の全体とつながっています。そして私は、〈わたし〉という語をなぜかしら必要とし、なぜかしら使ってしまう。
そうして使ってしまい、私から離れ、異物となった〈わたし〉は、結果的に、蝶番のような、裂け目のような、一種の開口部となるように思います。……ほかのひと、つまり、私ではない私に向かってひらかれた裂け目に。
***
〈わたし〉と私とは、どうちがうのか。
〈わたし〉とは、まず、私の発することばのなかに現れる「わたし」という語です。
そして、それを読んだり聞きとったりする他人にとっては、そのことばの全体を発したはずの特定の人物(カラダ)の存在のしるしとして、いわば「ヒトガタの目印」として働きます。
つまり〈わたし〉とは、「ものごとの発し手=ひとつのヒトガタ」という、強力な制度のようなものです。
一方で、書く私にとっては、〈わたし〉とはどのようなものでしょうか。
自分の感じていること、思うことを書こうとするとき、私はなぜかしら「わたしは…」という形式を使ってしまう。
それは、即自的な行為のように思えますが、じつは、自分からすこし距離をとり、自分自身をながめることです。
「わたしは…」とことばにするとき、その一瞬から裂けるように、距離が生じ、遅れが生じる。そして私は、自分がここにいて、なにかを感じているということを確認し、また、なにを/どんなふうに感じているのかを確認しつつ「設定」する――つまり、私の一部を「他」として切り離します。
(ここでは、〈わたし〉という強力な制度の働きのもとで、自分を「他」としたい、輪郭をはっきりさせたい、そしてそのことによって、自分自身と関係をもちたい…というような欲求が働いているように感じますが、その先はまだよくわかりません。)
〈わたし〉は、私という場から湧きあがるように生まれ出るのですが、いちど文字として書かれ(あるいは発音され)、外の空気にふれたとたんに、それは異物として在りはじめる。
そのように、切り離され、他/異物となった〈わたし〉に、あらためて同一化しようとする――イメージとしては、私の一部が、他/異物となった〈わたし〉に逆流するように流れこむ――ことで、私は、ほかのひととやりとりの可能な社会的な〈わたし〉=ヒトガタに部分的に「成る」のかもしれません。
(そして、このフジモトナホコと呼ばれる現象においては、その「成ること」につまずき転びつづけ、あるいは、目の前のヒトガタを凝視しすぎてその中に入れない――そんなことがくりかえされているのかもしれません。)
それは、総体としては、ことばの働きなのだと思います。
***
一方で私は、ものごとを発するヒトガタというより、場のようなものだと感じられます。
〈わたし〉がそこにあらわれ、ほかのさまざまなものごともあらわれ、通りすぎてゆく「場」そのもの、「地」そのものという感じです。
舞台しかない劇場のようなものかもしれません。
そして、〈わたし〉を見ている。
私という場は、〈わたし〉も、ほかのものごとも、同じように、離れて、見ている。
その視点と距離をもふくんでいる、……内的な「外」の次元(観客席?)も折り畳まれ、織り込まれているような、そして、その「場」じたいはどこまでいっても対象化しきれないような、二重性のある場です。
07 〈わたし〉と私
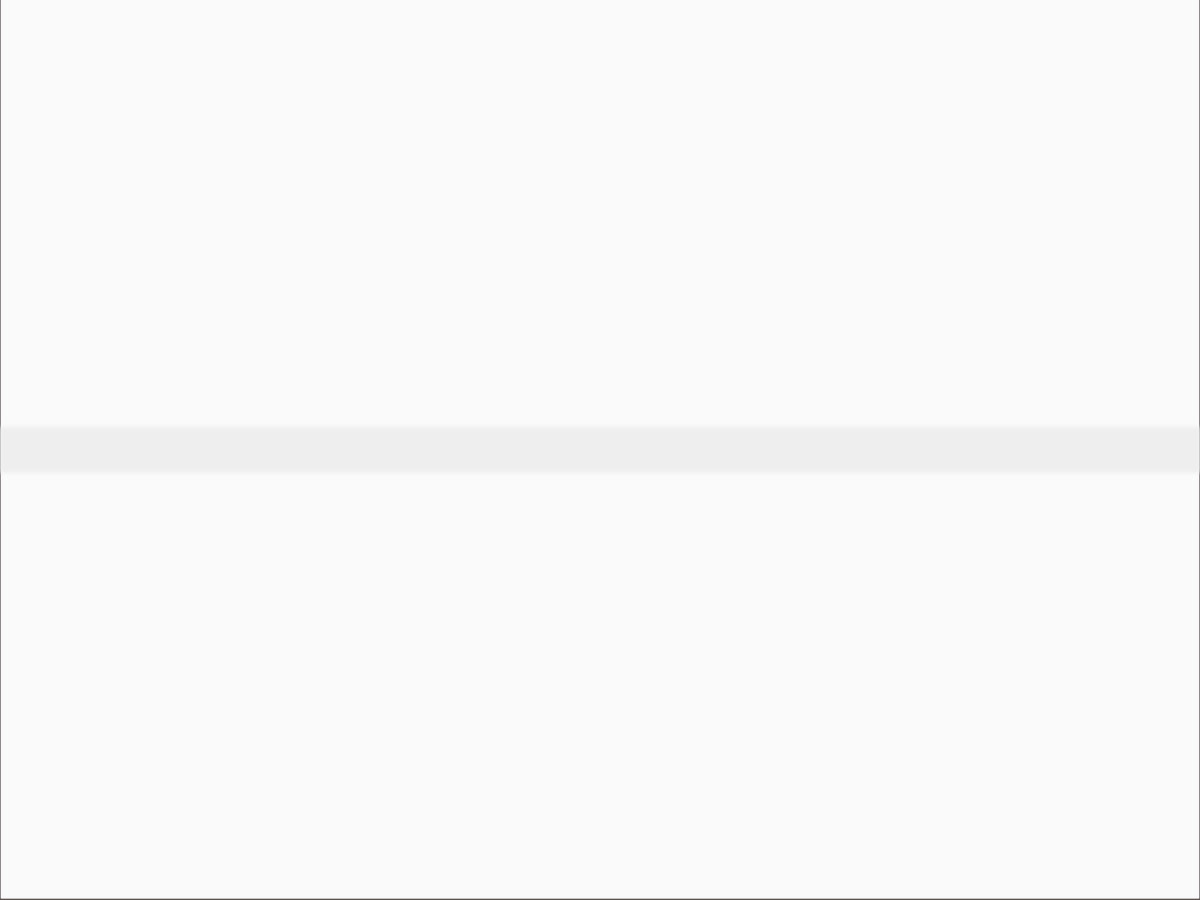
>>08 蝶番