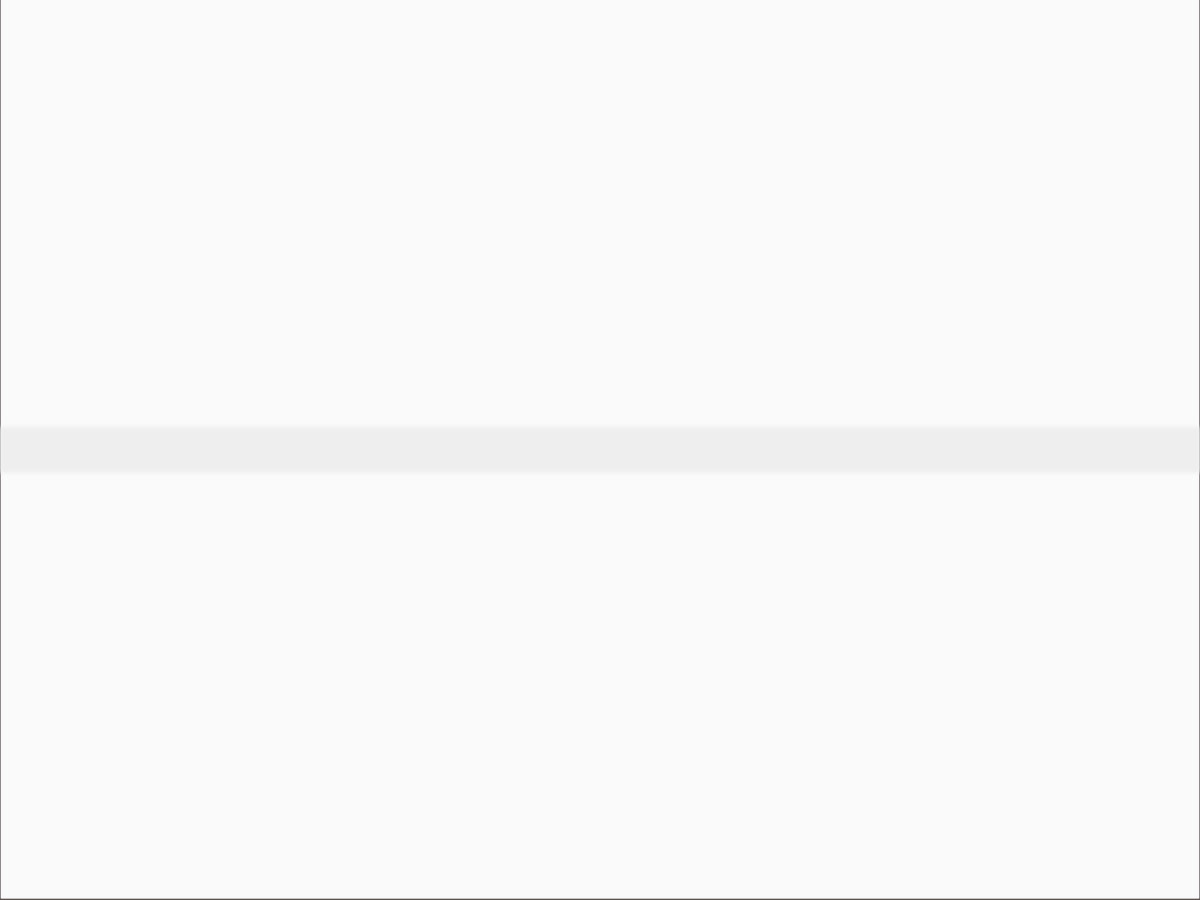作品をつくることは、目を閉じて手指を動かしつづけることに似ている。
制作しているあいだ、手は、自分が思っているのとはすこしズレた場所で動いているらしい。
つくられていくものは、自分にとって大切なものであるらしいとはわかるのだが、それがいったい「なに」なのかはわからない。
なにかのメタファーであるらしいのだが、その表す先は見えないまま、うごめき、育ってゆく。
そうして「作品」が成立し、私の手を離れる。しばらく時が経ったのち、私は自分に作品が「見える」ことに気づき、自分がすでになにかを贈られていたことに気づく。
***
しばらく前から、鏡文字を書く作品をつくっている。
自分の書く文字というものは、かなり気持ちが悪い。自分のからだの延長のようで、うまく距離がとれない。
他人の書く文字は、――たとえば友人のαさんなら「αさんの字」として、特徴やクセを見てとり、対象化してとらえられるのだが、自分の字は、とらえどころがなく、うまく対象化できず、これがなんなのか、よくわからない。
書いている指先のつづきのようで、自分のからだとの境界が、よくわからない。
それまではおもに他人の筆跡をトレースする作品をつくっていたのだが、鏡文字の作品から、なにもなぞらず、真似ず、素から「自分の字」を書くことになった。
しかし、鏡文字とはいえ、自分の字はやはり気持ちが悪くて、書く文字はどんどん小さくなり、肉眼ではほぼ読みとれないサイズになってゆく。
***
距離がとれないという点では、文字よりも声が、その最たるものだと思う。
声については、向かいあい、考えることが怖い。
***
あるとき友人が遊びに来て、上に書いたような、自分の文字や声への距離のとれなさについて話をした。
友人が帰ったあと、夕食を食べ、食器を洗っていて、ふと気がついた。
距離がとれなくて気持ちが悪いものといえば、「名前」がまさにそうだった。
気がついたときには自分の「しるし」としてくっついていた名前。
望んだ覚えはない。
この「名前」は、私のどこかに貼りついているらしいのだけれど、異物感があり、また、とても遠い。うまく見つめられない、そこに焦点があわない……どうにも、それを「見る」ことができない。
できることなら、名前をもちたくない。
名乗りたくない。
09 《補遺》 作品、文字、指、名前